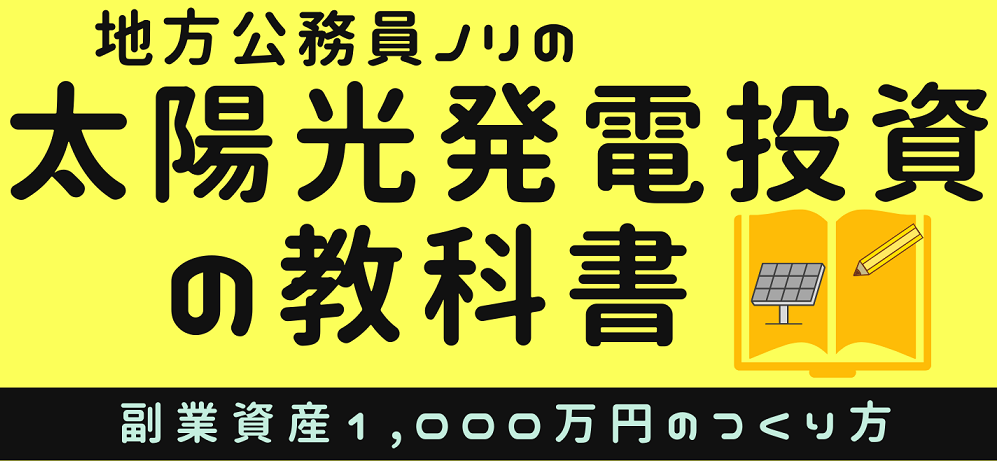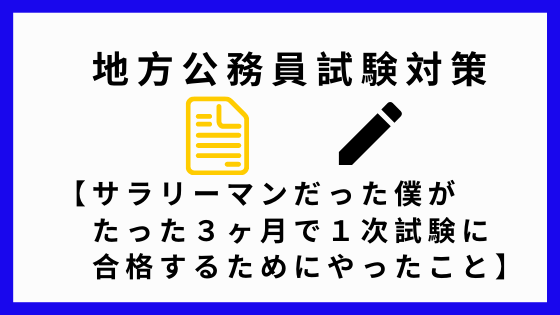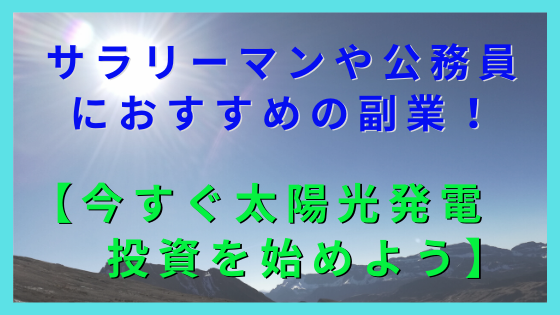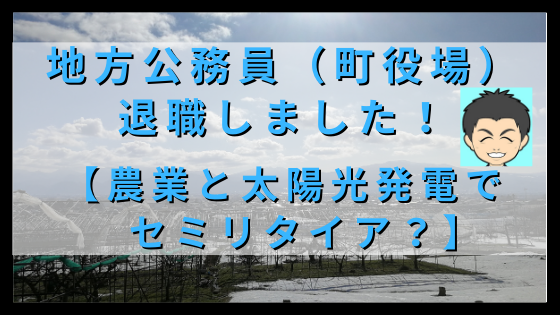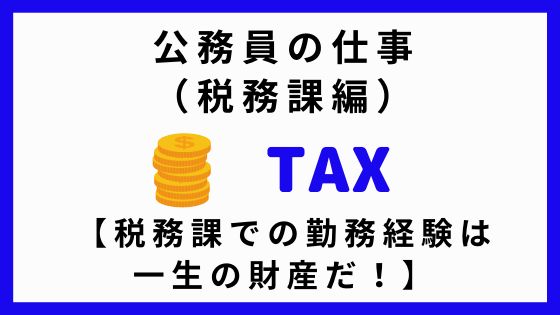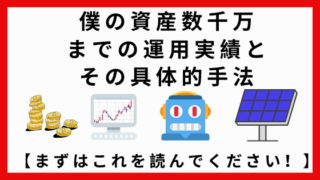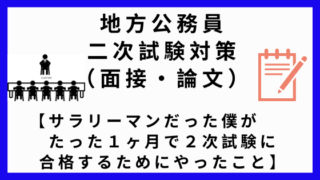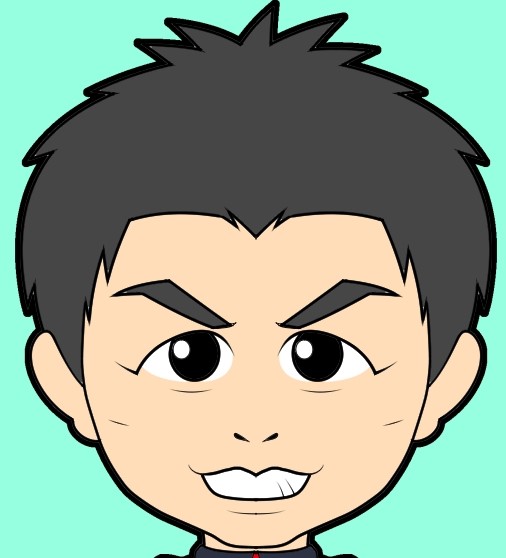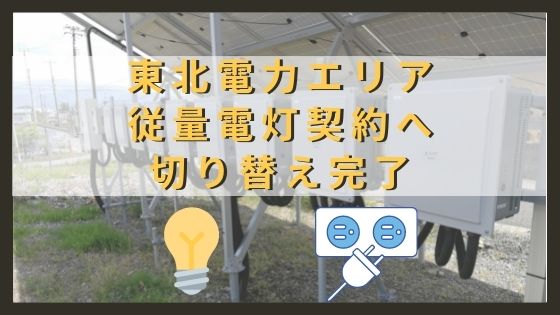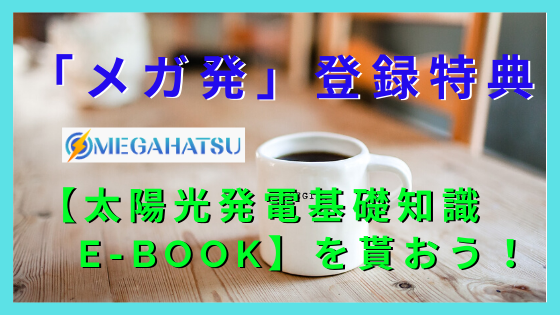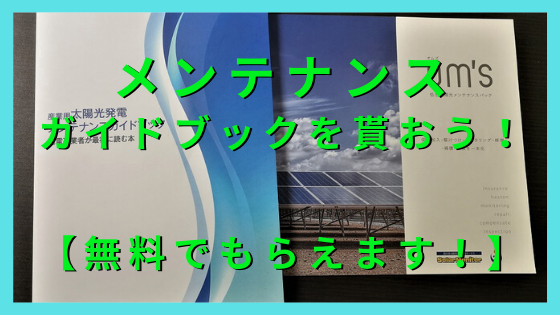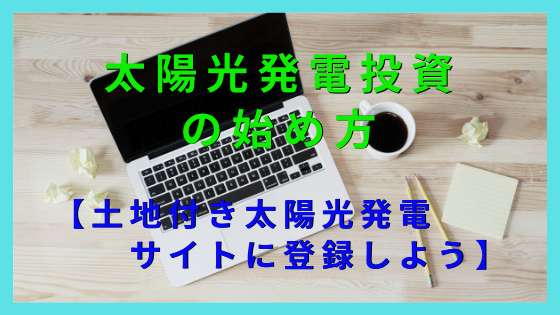こんにちは、現役町役場職員のノリです。
今回は、僕が民間企業でサラリーマンとして働きながら、たった3ヶ月の1次試験試験対策で試験に合格した方法について、どのようなことを行ったのかをまとめます。
正直、働きながら地方公務員になるというのは、かなりハードルが高いです。
しかし、僕のように働きながら公務員になりたいと思っている人、学生で学業と並行して公務員を目指している人もたくさんいると思います。
そんな方に、少しでも力になれるのであればと思い、僕がやったことと、当時の僕に向け、さらに効果的なアドバイスをまとめていきたいと思います。
本記事の内容
公務員試験対策で僕が実際行ったこと4つ
- 目標と目的を明確にする
- モチベーションを上げる環境づくり
- 勉強に集中する環境づくり
- 勉強の仕方を決める
以下、詳しく説明します。
1、目標と目的を明確にする
まず、公務員試験対策だけでなく、何かに挑戦する際にも共通することですが、目標と目的を明確にすることが最も重要になります。
ここがぶれてしまうと、どうしようもありません。
必ず、自分の目標が何で、何のためにそうなりたいのか、明確にしてください。
例えば、僕であれば、
目標:地元の○○町役場に入る
目的:地元の体育館で働きたい、地元の町でスポーツ振興がしたい、地元の町をバスケットボールで有名な町にしたい
といった、目標と、目的がありました。
目的が明確でないと、なんのためにその目標をクリアしようとしているのかがわからなく、辛い環境や困難な状況になった時に、挫折してしまいがちになります。
この時、目的が明確であれば、どんなに辛くてもモチベーションを保つことが可能になります。
試験勉強が辛い、なかなか合格ラインに達していない、そんなときに役立ちます。
自分の目的が明確でない方は、まずはこの点をしっかりと決めてください。
2、モチベーションをあげる環境づくり
なぜ、自分は公務員になりたいのか、公務員になって何をしたいのか、この目標と目的が明確になったら、次は、公務員試験試験対策をする上でのモチベーションを上げる環境づくりを行いましょう。
モチベーションを上げる方法は3つです。
- 公務員の志望理由(目的)を紙に書き、目に付く位置に貼る
- 公務員になった自分を想像する
- 公務員になると周りに宣言する
この3つは、勉強に行き詰まった時、集中できなくなったとき、自分のモチベーションを上げるのに非常に役立ちました。
では、ひとつずつ詳しく見ていきます。
1、公務員の志望理由(目的)を紙に書き、目に付く場所に貼る
公務員になりたい理由(目的)を決めたら、紙に記入しましょう。
そして、その紙を部屋の壁など必ず目に付く位置に貼りましょう。
試験勉強をする場所から目に付く位置に貼るのが良いと思います。
そうすることで、ただ目的を頭で考えるよりも、紙に書き、毎日目に見えるようにしたほうが、意識する回数が増え、その意識で行動が変わってきます。
公務員試験は、とにかく試験対策の勉強が苦痛になる時期がきます。
この時に、この目的を見える位置に貼ることで、行動を継続する、モチベーションを維持することができます。
2、公務員になった自分を想像する
次に、公務員になった自分をイメージしてください。
毎日、何度もイメージをしてください。
例えば、
- やっと念願の公務員になれた。
- 毎日定時で帰り、アフター5に好きなことができる。
- 土日は休みだ。
- 給与は毎年昇給で年々増える。
- 営業ノルマもないし、最高だ!
その状態を想像できれば、OKです。
そのイメージができることで、その状況になりたいと思う気持ちが、強くなり、弱い自分への意識づけができるようになります。
- この辛い時間(試験勉強)がずっと続くわけではない
- 今のこの試験勉強を我慢すれば公務員になれる
- 今、この時間だけ頑張ればいい
- 試験までの残り数ヵ月を乗り越えればいいんだ・・・
僕は、こう言い聞かせ、乗り越えられました。
3、公務員になると周りに宣言する
これについては、合う人、合わない人がいると思います。
僕の場合は、地元の友人や、大学時代の友人に、公務員に転職するとはっきりと宣言し、あえて自分にプレッシャーをかけました。
公務員になるために、勉強しなければならない、みんなに宣言したから中途半端に試験勉強をするわけにいかない、といったことです。
周りに宣言し、合格できないほどかっこ悪いことはありません。
自分にプレッシャーをかけ、それを乗り越えるために、あえて宣言し行動しました。
ただし、これに向かないと思う人はやる必要はありません。
誰にも言わず、コツコツする方が向いている、宣言してしまうと逆にプレッシャーがかかってダメだという人もいるはずです。
自分がどちらの人間か、自分が一番わかると思いますので、やるかやらないかはお任せします。
以上が、モチベーションをあげるためにやったこと3つです。
ここがしっかりとできれば、第一関門は突破です。
3、勉強に集中する環境づくり
勉強に集中する環境づくりのために、僕は2つのことを行いました。
- 勉強の邪魔するモノ・誘惑するモノをすべて捨てる
- 趣味・サールを休止する
1、勉強の邪魔するモノ・誘惑するモノをすべて捨てる
勉強の邪魔をするモノを捨てるということですが、これは、僕の場合は独学で自宅で学習する環境だったからです。
よって、まずは、予備校か、独学がという視点で考えたとき、予備校へ通えるという人は今すぐ予備校へ行ってください。
公務員試験に特化した講師、カリキュラム、周りにいるライバルと競いあえる環境、予備校には、それらがすべてそろっています。
しかし、僕のように働きながらとなると、時間や、お金の関係で、独学を選択せざるを得ない方もいると思います。
そんな方は、まず、勉強の邪魔をする、誘惑するものをすべて遮断してください。
テレビ、スマホ、SNS、ゲーム、マンガなど、様々な誘惑が周りにはあります。
それに負け、勉強ができなくなります。
途中で気分転換にスマホをいじったりすると、あっという間に勉強時間以上にスマホを触っている時間が長くなってしまう、なんてことはないでしょうか?
その状態が、試験合格から遠ざかることになります。
公務員試験は勉強の質も重要ですが、時間をかけての反復学習が必要です。
遊んでいる暇はありません。
それらを、捨てる、もしくは利用できない状態にしましょう。
僕は独学で、しかも自宅で公務員試験勉強を行いました。
そこで、マンガはすべて売却し、テレビはクローゼットの中にしまいこみ、すぐに見れない状態にしました。
自宅では勉強できないという方は、図書館やファミレスなどで勉強するのも良いと思いますので、自分が一番集中できる環境を見つけて、誘惑に負けてしまいそうなものがあれば、すべて排除してしまうくらいの気持ちで、すべて片付けてしまいましょう。
2、趣味・サークルを休止する
趣味、クラブ活動、大学生であればサークル活動などの時間を、すべて試験勉強する時間へ切り替えましょう。
これは、自分が1番に考えることに時間を集中させるということです。
公務員試験はそんなに甘いものではありません。
好きなことをしながら、片手間で勉強をして公務員になれるなら、苦労しません。
自分が好きで行っていることを一定期間やらずに、すべて勉強時間へ捧げてください。
僕は、バスケットボールを週に2~3回行っていましたが、3か月間1度も行かずに我慢し、その期間は平日夜も土日もすべて勉強に捧げました。
この時期を乗り越えて、試験に合格すれば、好きなだけバスケットボールができるということをイメージし勉強に集中することができました。
4、勉強の仕方を決める
- 僕が実際に行ったことは以下の3つです。
- 試験内容を調べる
- 参考書の選び方
- 参考書の活用の仕方
1、試験内容を調べる
これは、自分がなりたい公務員の試験内容をしっかりと確認しましょう。
自分が勉強する方向を間違わないようにしましょう、ということです。
極端な例を言うと、例えば、
地方公務員といっても、様々な職種、試験があります。
消防士になりたいという人が、実技試験の対策ばかりしていても、筆記試験対策をせず本番を迎えたら、よほど学力が備わっている人でない限り、不合格になってしまいます。
地方公務員にも様々ありますが、大卒であれば基本的に地方上級試験の対策が必要です。
高校までの5教科で教わる内容だけでなく、法律などの専門分野まで学習しなければなりません。
試験内容を調べ、自分の今の環境で対応できるのかどうか、予備校へ行くべきか、独学で良いのか、といったことを判断しましょう。
ちなみに、僕が今働く町役場は、地方初級レベルの試験しか行っていない自治体でした。
僕のような大卒でも、試験内容は高卒の人と同じ試験になります。
その点が、僕が働きながら、独学で短期間集中学習で合格することができた理由のひとつです。
上級試験で法律などの専門分野まで勉強するとなると、正直3ヶ月では厳しかったと思います。
それを踏まえて、どこで働くということを抜きにして、ただ公務員になりたいってだけの方へアドバイスです。
私がお勧めするのは、町役場などで初級試験しか行っていない自治体、もしくは社会人枠で法律専門分野などを免除してくれる社会人枠を設けている自治体の試験を受けることです。
そのような自治体をしっかりと探し、自分のやりたいこととマッチしていれば、働きながらでも独学で対応できると思います。
実際に私が3ヶ月の勉強だけで合格しているので、間違いないです。
ここ、重要なので、もう一度、言います。
どこでもいいからただ地方公務員になりたい方は、
町役場などで初級試験しか行っていない自治体、
もしくは
社会人枠で法律専門分野などを免除してくれる社会人枠を設けている自治体
の試験を受けてください。
そうすることで、一気にハードルは下がるはずです。
2、参考書の選び方
次に独学で勉強する人の参考書の選び方についてです。
予備校を選択した場合は、予備校の指定する教材だけで大丈夫です。
予備校が指定する参考書以外に手を出さないでください。
僕のように独学を選んだ人についてですが、まずは、自分の行動エリアで一番規模の大きな本屋に行ってください。
その本屋で目立つ位置に置いてある公務員試験対策の参考書なら、まず外れることはないと思います。
その本屋で参考書の種類としては、3種類選んでください。
- 模擬試験1冊
- すべての分野の要点がまとまった参考書1冊
- 試験の過去問集1冊
の3冊です。それ以上は購入しなくてOKです。
参考書を選ぶ方法ですが、本屋などで参考書を手に取り、中身をパラパラとめくり、ビジュアル的に自分に合うか合わないかを判断して選ぶだけでいいと思います。
見にくい、勉強する気にならない、わかりにくいといった個々人差はあると思うので、これならわかりやすい、勉強が継続できそうだ、といった参考書を探して選ぶだけでいいです。
僕は、一番初めに本屋に行って、2時間かけてこれだという参考書を3冊選びました。
自分に合う参考書を慎重に選んでください。
3、参考書の活用の仕方
独学で勉強することを選び、上記の参考書を選んだあとは、参考書の活用方法について、具体的に説明いたします。
予備校を選択した方は、予備校のカリキュラムに従って進めてください。
模擬試験の参考書を使い、自分のレベルを把握する
まずは1番最初に模擬試験をやってください。
それで現時点での自分のレベルを把握することができます。
公務員試験ってどんなものなのだろう、公務員試験ってこういった問題がでるのか、といったことを感じ取ることができます。
また、合計点数まで自分がどれくらい足りないのか、知ることができます。
僕の場合は、100点満点の45点くらいで、合格圏内の7割にはまだまだ遠く、かなり焦った記憶があります。
それで、勉強にスイッチを切り替えることができました。
すべての分野がまとまった参考書で基礎力を付ける
模擬試験を受け、自分の現状を把握した次は、とにかく、すべての分野の要点がまとまった参考書を1からノートに書き写しながらすべてを暗記するつもりで最低3周は勉強してください。
僕は、ノートに書かないと覚えられない方だったので、とにかくノートに書きこみました。
そして、声に出して覚えました。
個々人で暗記しやすい方法で構いませんので、1周終わったら、2周目、次に3周目と、最低でも3周はこなしてください。
よく陥りがちなのが、2周くらい勉強することで、暗記できたと思い他の参考書を購入してしまうことです。
何冊も買うのではなく、これだという1冊を決め、最低3周、余裕があればそれ以上行ってください。
人間、覚えているようで、覚えていないものです。
とにかく反復学習をしてください。
そして、絶対的な自信がつくほど完璧に覚えたとなったら、次の参考書に手を出してください。
試験の過去問集で試験の傾向をつかむ
先ほどの分野ごとの勉強を進めながら、一つの分野が終わるたびに、対応する分野の過去問集を解いてください。
これにより、その分野の習熟度や公務員試験の傾向をつかむことができます。
これも、何度も問題を解いてください。
とにかく反復学習です。
できれば過去問集にはすぐ書き込まず、過去問題集のコピーを取るか、問題の回答だけを別途ノートに記入して、ノートで採点するなどして、何度も活用できるようにしてください。
僕はこれで実際に町役場に合格することができました。
読んでもらえばわかるように、特別なことはしていません。
正しいやり方で、コツコツと反復して学習してきただけです。
しかし、これが簡単なようで、難しいです。
途中で挫折しそうになることもあると思います。
そんな時は、公務員試験に合格した後の幸せな自分をイメージし、モチベーションを上げて、取り組んでみてください。
まとめ
公務員試験対策で僕が行ったこと
- 目標と目的を明確にすることでモチベーションあがり、行動が変わった
- 試験勉強は非常に辛いので、そのモチベーションを上げるための環境をつくった(紙に書き見える位置に貼る、公務員の自分を想像する、周りに宣言する)
- 勉強の邪魔をするものを捨て、趣味や活動を休んだことで、勉強に集中できる環境をつくった
- 試験内容を調べ、正しい参考書を選び、正しい方法で活用した
公務員を目指す方は、僕が行ったことを参考に、取り組んでみてください。
以上が、僕が、民間企業でサラリーマンをしながら、地方公務員試験に合格するために行ったことです。
これを読んでひとりでも公務員の仲間が増えてくれたら嬉しいです。
最後まで読んでくれてありがとうございました。